テレビCMや情報番組でもたびたび耳にする『善玉菌』という言葉。
腸内環境を整えるには欠かせない存在です。
でも、善玉菌って何なのか、何をしてくれるのかって聞かれたら困ってしまうかもしれません。
実は健康の維持や免疫アップ、精神の安定など、善玉菌はいろんな面で私たちを超サポートしてくれています。
ここでは、善玉菌のチカラや、その力を効果的に高めるための方法について詳しくお伝えしていきます。
さっさと善玉菌の増やし方を見たい方は目次の「 3. 善玉菌を増やそう!!」から見て下さいね^^
それではいってみましょー!
“善玉菌”ってなに?
ショッキングないい方をすると、私たち人間の体は、たくさんの微生物に寄生されています。
…といっても、『寄生獣』のようではありません。笑。
微生物だけが利益を得るわけでなく、寄生されることによって人間にもメリットがあるという“ミギーと主人公・新一”や“クマノミとイソギンチャク”のような関係ですね。
(厳密には寄生ではなく“相利共生”といいます)

私たちの肌や口の中などに棲みついている微生物もいて、健康な人には害を及ぼすことがないこのような菌を常在菌といいます。
このうち、腸に棲んでいて、その生産物質が人に良い影響を与える菌のことを、特に“善玉菌”と呼んでいるのです。
常在菌の中には、体力が低下したり環境が変化したりすると、人に害を与える菌もいます(ブドウ球菌や連鎖球菌などの日和見菌)。
しかし、善玉菌は他の常在菌と違って、病気の人にも害を与えることはありません。
ヒトの腸の長さはおよそ10mですが、この中に1人当たり500種類以上の善玉菌が100~1000兆個も棲んでいます。
重さにすると、なんと1.5㎏以上!
かなりの量ですよね!
ただし、善玉菌の生息数にはかなりの個人差があります。
その理由はのちほど。
ヒトの善玉菌には有名な“ビフィズス菌”や、ガセリ菌・ブルガリア菌・カゼイ菌などの“乳酸菌”、”納豆菌“や”酵母“などがいます。
「えっ!?ビフィズス菌と乳酸菌って違うの?」と思った方、こちらの過去記事をどうぞ↓
善玉菌の働き
こんなにたくさんの善玉菌たち、一体、私たちの体で何をしているのでしょうか?
ざっとこんな感じです↓
善玉菌の働き
1. 病原体からの防備
2. 食物繊維の分解・消化
3. ビタミン類の生成
4. 神経伝達物質の生成
5. 免疫の生成・強化
それでは詳しく見てみましょう。
善玉菌の働き①:病原体からの防備
実は微生物の仲間って“縄張り意識”が強いんです。
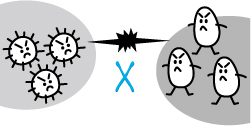
もちろん、自分自身を守るためなのですが、ほかの微生物がテリトリーに入らないようにいろんな方法で守っています。
その方法で有名なのが、カビの仲間が生成する“抗生物質”です。
これがカビの周りにあると、多くの菌はカビに近寄ることができません。
これを利用して、私たちが服用する薬が作られているわけです。
善玉菌であるビフィズス菌や乳酸菌も、腸の中に縄張りを持っています。
ヒトの腸には食べ物のカスがたくさんありますよね。
これは善玉菌にとっても他の微生物にとっても、魅力的な生息環境なわけです。
ですから、縄張りを奪われないように敵に備えて乳酸・酢酸・酪酸といった“酸”を生成しています。
酸は周りのpHを下げ、悪玉菌が生息しにくい環境に変えてくれるのです。
ビフィズス菌や乳酸菌の敵となる微生物は私たちにとっても敵です。
この敵のことを“悪玉菌”といい、大腸菌やウェルシュ菌など病気を引き起こす原因となったり、発がん性物質を作ったりする菌を指します。
善玉菌は悪玉菌が腸に棲みつこうとするのを阻止し、私たちが病気にかからないように守ってくれているんですね。
善玉菌の働き②食物繊維の分解・消化
私たちが摂取する大事な栄養の一部“食物繊維”。

ところが人間は食物繊維を分解する消化酵素を持っていないため、分解することができません。
これを代わりに分解してくれるのが善玉菌です。
善玉菌が分解することにより私たちが吸収できる物質になり、大切なエネルギー源として利用できるようになるのです。
おもしろいことに、私たちの腸は自力で分解できない食物繊維を吸収することを前提に機能しています。
もし、善玉菌が食物繊維を分解してくれなかったら、大腸は機能障害を起こすそうですよ。
善玉菌に甘えつつ感謝!!ですね。
善玉菌の働き③ビタミン類の生成
私たち人間はビタミンを自分の体内で合成することはできません。
ですから、食事などで体外から補給する必要があるのです。
ビタミンは体内で起こる様々な反応の“潤滑油”のように働きます。
ビタミンが不足すると、必要な反応が行われなくなり、体の不調につながるわけですね。
 ビタミンを合成できるのは、植物や微生物です。
ビタミンを合成できるのは、植物や微生物です。
そして!
私たちの腸に棲む善玉菌も、ビタミンを合成できます!しかも腸の中で!!
善玉菌が合成できるのはビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンB12・ビタミンK・葉酸・パントテン酸・ビオチンなどの水溶性ビタミンです。
食事などから補給していても不足しがちなビタミン類ですが、体内で、しかも消化管の中で合成してくれるなんて、善玉菌サマサマですね。
善玉菌の働き④神経伝達物質の生成
善玉菌はビタミンの他にも、私たちの体に作用する物質を合成しています。
それが、“ドーパミン”や“セロトニン”といった神経伝達物質です。
神経伝達物質とは、神経から神経へと伝令を行う“メッセンジャー”で、目的となる器官の細胞に興奮または抑制の反応を起させる化学物質のことです。
ドーパミンには脳に幸福感や快感を与え、ヤル気を引き出したり集中力を高めたりする働きがあります。
セロトニンは“幸せホルモン”とも呼ばれる物質で、心身の安定や心の安らぎなどを感じさせてくれるほか、止血作用などもあります。

神経伝達物質は神経のシナプス前細胞で作られるものもありますが、善玉菌によって作られたものも、きちんと脳に到達します。
脳と腸ではだいぶ距離がありますが、この2つの関係は『脳腸相関』と呼ばれていて、ストレスを感じるとお腹が痛くなるのもその1つです。
このように、善玉菌が作り出した神経伝達物質が人の精神面に良い影響を与えることが大規模調査でも確認されており、善玉菌の新しい効果として注目されています。
善玉菌の働き⑤免疫の生成・強化
善玉菌の働きのうち、いま一番期待されているのが“免疫への効果”です。
インフルエンザの予防効果が高いとして話題になった『R-1ヨーグルト』や、免疫系の司令塔『プラズマ乳酸菌』に代表されるように、多くの機能性ヨーグルトが免疫力アップに効果があるとして売られていますね。


それもそのはず。
私たちの免疫力の70%は、腸内の善玉菌と腸の働きで作り出されているのです。
特に、善玉菌の中でも数が多く効果も高いビフィズス菌は、その生息数が健康状態に深く関係しているとして重要な菌です。
東京大学名誉教授の光岡知足先生によると、ビフィズス菌を20%にすることが健康にとって理想的なのだそうですが、現実には10%程度の人が多いそうです。
善玉菌、特にビフィズス菌が増えると免疫機能がアップしたり正常化したりするので感染症にかかりにくくなりますし、アレルギー症状の改善にも効果があります。
アレルギーでお悩みの方、こちらの過去記事もどうぞ!!
善玉菌を増やそう!!
こんなにスゴイ働きをしてくれる善玉菌がもっと増えてくれたら、その効果もアップしますよね。
腸にはいろんな善玉菌が棲んでいますが、消化管の末端である腸の中は酸素が少なく、乳酸菌の生育にはあまり適していません。
その点、ビフィズス菌は酸素がない方が元気になり、前述の善玉菌の5つの働きへの貢献度も高い菌です。
…というわけで、効果的に善玉菌を増やすなら、ビフィズス菌に増えてもらうのがお得です。
それではその方法を紹介しましょう!
- 食物繊維やオリゴ糖を摂る
- 乳酸菌などを含む発酵食品・サプリメントを摂る
- ビフィズス菌を摂る
どういうことか、もう少し詳しく説明しますね。
善玉菌の増やし方①食物繊維やオリゴ糖を摂る
まず、一番重要なのは、エサを与えることです。
ペットだってそうですよね。
エサの基本は、イヌならイヌ用、ネコならネコ用、ビフィズス菌にはビフィズス菌用…ということです。笑。

↑こんな感じでビフィズス菌(善玉菌)がエサを待っています。笑
専用のエサには、その生物に適した栄養が配合されています。
先ほどの「善玉菌の生息数には個人差が大きい」というのは、その人が「エサをきちんと与えているかどうか」ということなんです。
では「ビフィズス菌に適したエサは何か」というと、食物繊維やオリゴ糖、他微生物の菌本体や生産物質です。
すでに述べた通り、私たちが消化できない食物繊維はそのまま腸へと運ばれます。これがビフィズス菌のエサになるわけですね。
これを踏まえると、食物繊維を多く含むゴボウなどの野菜類を積極的に摂ると効果的なんですよね。
ゴボウは硬くて苦手…という人はブロッコリーがおすすめ!柔らかくて食べやすいわりに、食物繊維の含有量も多いんです。
そして、オリゴ糖もビフィズス菌の大好物!
オリゴ糖も私たちが消化できない物質なのでそのまま腸まで届きます。
更に言うと、オリゴ糖はビフィズス菌の増殖が確認されている物質ですから心強いですね!低カロリーの甘味料として市販されています。
善玉菌の増やし方②乳酸菌などを含む発酵食品・サプリメントを摂る
ビフィズス菌は細菌の体(菌体)や生産物質(ビタミンなど)などを食べます。
ですから、ヨーグルトやキムチなどの発酵食品や、乳酸菌含有のサプリメントなども良いエサになってくれます。

サプリメントはとりあえず何か試してみるというのが大切ですね^^
善玉菌の増やし方③ビフィズス菌を摂る
ビフィズス菌を直接増やしたいという場合は、ビフィズス菌入りの食品を摂る方法もあります。
ただし、ビフィズス菌は胃酸に弱いので食前の摂取は避け、カプセルなどで保護されたビフィズス菌や耐酸性の高いタイプのものを選ぶようにしましょう。
なお、ヒトの腸には2~4菌種のビフィズス菌しかみられないそうです。
となると、摂取したビフィズス菌が自分の菌のタイプと違っている場合、定着しないパターンもあります。
エサとして摂った菌体や生産物質についても同様で、自分の腸に棲んでいるビフィズス菌と相性が悪いと、増えてくれないことになります。
こういった「あたり・はずれ」に惑わされたくない人は、ビフィズス菌の好き嫌いがない食物繊維やオリゴ糖の摂取をおススメします。
さいごに
私たちの健康と密接なつながりをもつ善玉菌。
たくさん増えてもらって、健康に貢献してもらいましょう!!

エサは毎日、忘れずにあげてくださいね(笑)♪
こちらの記事でも善玉菌について触れていますので、ぜひご覧ください!

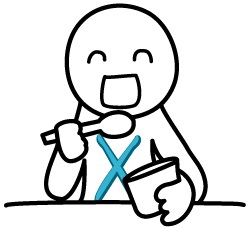

 管理人ニノがお送りする、2018年時点で、『便秘とダイエットに悩む女性』にとって、最も原料的にオススメな乳酸菌サプリです。(皆さんだいたいここで悩まれるので)
管理人ニノがお送りする、2018年時点で、『便秘とダイエットに悩む女性』にとって、最も原料的にオススメな乳酸菌サプリです。(皆さんだいたいここで悩まれるので)








正しい乳酸菌の知識を学び、あなたに美容健康ライフを!!!